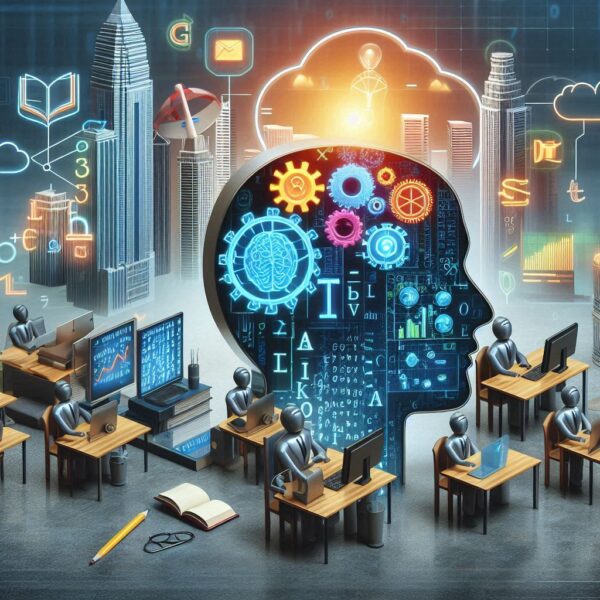
こんにちは、プラットフォームxコーチングの八木橋ショーガックです!
今日は、2011年4月の苫米地英人さんと出口汪さんの対談から学んだ「現代文の本質」と「論理的思考の重要性」についてお話しします。
フォレスト出版の『奇跡の「話す」「書く」技術~脳を活かす奇跡の「メタ意識」コミュニケーション術』 出口汪 著(2011/8/20)の読者特典音声が出典です。
現代文は「現代文学」ではない!
昔の「現代文」という科目は、現代の文学を読むことが主な目的でした。
しかし、今の現代文はそうではありません。
実際には、 「論理的に考える力を鍛える科目」なのです。
かつて、蘭学の翻訳を通じて科学の知識を学ぶ訓練が行われました。
これは現代の大学教育の、外国の論文を読み、自分でも論文を書けるようになるための訓練につながります。
つまり、「言語を使って論理を組み立てる力」が求められていたわけですね。
頭がいい人は「記憶」にこだわらない?
苫米地英人さんは、「頭がいい人は復習を重視しない」と話しています。
なぜなら、本当に理解しているなら記憶に頼る必要がないからです。
予習も復習も不要で、一度聞けばすぐに理解できる人がいます。
これは生まれつきの能力の違いもあるでしょう。
でも、多くの人にとって重要なのは 「理解のプロセス(論理、ゲシュタルト)を意識すること」です。
フェアな世界とは何か?
「生まれつきの病気は確率の問題であり、どうしようもない。でも、生まれてきたこの世の中自体はフェアであるべきだ」と苫米地英人さんは言います。
フェアな世界を作るためには、「論理的な思考が根本にあるべき」だと考えます。
感情に流されるのではなく、検証可能な空間、つまり論理が通る世界を作ることが大切です。
言語と論理の関係
言語には「人工言語」と「自然言語」があります。例えば、数学やプログラミングの言語は人工言語。日常会話や小説は自然言語です。
現代文の読解力とは、「自然言語を論理的に理解する力」です。
だからこそ、理科系教育も重要になってきます。
「数学ができないと困るよ」と言われるのは、数学が論理的思考のトレーニングになるからです。
感情と論理のバランス
では、論理だけでいいのか? そうではありません。
論理的に考え、抽象的な空間に入り込み、そこで徹底的に思考することが大事です。
しかし、 人間相手にコミュニケーションをとる以上、最終的には情緒の世界に戻る必要があります。
大切なのは、「主観→論理→主観」のサイクル。
-
まずは自分の考え(主観)を持つ。
-
それを論理で整理する。
-
そして、人の気持ちを考慮した上で伝える。
論理空間だけに閉じこもってしまうと、他者とのコミュニケーションが成立しません。
だから、論理と感情のバランスが大切なのです。
コミュニケーションの本質
「あなたの人格はバカにしていない。あなたの論理がバカなんです。」
これは強烈な言葉ですが、本質を突いています。
議論をするときに、相手の人格を否定するのではなく、その人の論理に対して指摘をすることが重要です。これは、組織のコーチングでも同じです。
組織の成長にはコーチングが必要
「組織のゴールを共有しよう。そのために、プロのコーチを入れよう。」
組織の成長には、個々のメンバーが共通のゴールを持つことが不可欠です。
そして、そのゴールを正しく設定し、実現するためには、プロのコーチングが必要になります。
教育の限界は想像力の限界
「想像力の限界が、教育の限界だ」と言われます。
教育の目的は、知識を詰め込むことではなく、想像力を伸ばすことです。
もし、想像力を失ってしまったら、社会は発展しません。
日本は民主主義国であるので、「川端康成の文章みたく書くべき」は民主主義国ではない。
出口汪先生のような先生を
親が「先生をもっと偉くしろ!」と言って、投票するいいです。
と、苫米地博士が言っていました。
まとめ
・現代文は「論理的思考の訓練」
・頭の良い人は理解を重視し、記憶に頼らない
・フェアな世界を作るには論理的な思考が不可欠
・言語空間の理解が教育の鍵
・論理と感情のバランスを取ることが重要
・議論では人格ではなく論理を評価する
・教育の本質は想像力を伸ばすこと
論理的に考えながらも、情緒の世界にも戻る。
そんなバランスを持つことが、新しい時代に必要なスキルです。